カンファレンス成功の鍵は運営にあり!企画から実行までプロが教える完全ロードマップ
%20(1).jpg)
「盛況だったはずが、結局事業にどう繋がったか分からない…」カンファレンス運営で、こんなお悩みを抱えていませんか?多忙な担当者様にとって、成果の出るイベント運営は簡単ではありません。 本記事では、イベント制作のプロである株式会社REIGETSUが、数々のカンファレンスを成功に導いた実践的ノウハウを初公開。企画立案からKPI設定、緻密なタスク管理、当日のトラブル対応まで、明日から使える具体的なロードマップを提示します。「やりっぱなし」を卒業し、ビジネスを加速させるイベントを実現しましょう。
監修 事業本部 主任 宮木翔太
イベントの企画から運営まで幅広く対応し、数多くの進行台本や運営マニュアルを制作してきました。 施工段階から関わった実績もあり、より精度の高い運営を実現しています。 特に、展示会イベントやトークショーの案件に多く携わり、運営統括としても多数の現場を成功に導いてきました。 細部までこだわった丁寧な進行管理と、円滑な運営を強みとしています。
目次
-
なぜ、多くのイベントは「やりっぱなし」で終わってしまうのか?
-
【STEP1:企画編】成功の9割が決まる!カンファレンス企画の要諦
-
・最重要!イベントの目的(KGI/KPI)を明確にする
-
・誰に、何を届けるか?ターゲットと提供価値の具体化
-
・企画の骨子を固める「6W2H」フレームワーク活用術
-
-
【STEP2:準備編】抜け漏れゼロへ!半年前から始める逆算タスク管理
-
・全体像を把握する!WBSを使ったタスクの洗い出し
-
・必携!イベント運営マニュアル作成の3つの極意
-
・集客を最大化するプロモーション戦略
-
-
【STEP3:当日運営編】想定外を乗り越える!スムーズな進行を実現する現場力
-
・本番前の最終チェック!リハーサルと機材確認のポイント
-
・"おもてなし"の第一歩!スマートな受付・誘導オペレーション
-
・プロが実践するトラブルシューティング術
-
-
【STEP4:開催後編】次につなげる!イベント価値を最大化するフォローアップ
-
・効果測定とデータ分析で成果を可視化する
-
・熱量を保つ!参加者へのお礼メールとアンケート術
-
・社内への成果報告とナレッジの蓄積
-
-
カンファレンス運営に課題を感じたら、プロに相談という選択肢も
なぜ、多くのイベントは「やりっぱなし」で終わってしまうのか?
%20(1).jpg)
「盛況のうちに終了した」はずのカンファレンス。しかし、その実態が「集客に追われ、当日はバタバタ。結局、事業にどう繋がったのか分からない…」という結果に終わってしまうケースは少なくありません。
企業のイベント担当者の皆様は、日々の業務と並行して、この複雑で多岐にわたるイベント運営を担わなければなりません。その結果、目の前のタスクをこなすことに精一杯になり、イベント本来の目的達成が見過ごされがちになるのです。
この記事では、イベント制作のプロである私たち株式会社REIGETSUが、数々のカンファレンスを成功に導いてきた実践的なノウハウを、4つのステップに分けて具体的に解説します。単なる手順の紹介ではなく、「成功するイベント」と「やりっぱなしのイベント」を分けるプロならではの視点を盛り込んでいます。ぜひ、貴社のカンファレンス運営にお役立てください。
【STEP1:企画編】成功の9割が決まる!カンファレンス企画の要諦
%20(1).jpg)
イベントの成否は、企画段階で9割が決まると言っても過言ではありません。ここでは、ブレない軸を作り、成功への最短距離を描くための企画の立て方を解説します。
なお、カンファレンスの開催を初めて検討されている方は、まず「カンファレンスとは何か?」を解説した以下の記事からご覧いただくのがおすすめです。
→カンファレンスとは?その意味から企画~開催の流れまで徹底解説
最重要!イベントの目的(KGI/KPI)を明確にする
まず、「なぜこのカンファレンスを開催するのか?」という目的を、誰にでも説明できるレベルまで具体化しましょう。曖昧な目的は、その後の全ての判断を鈍らせる原因となります。
プロの視点: 私たちプロは、目的を「KGI(重要目標達成指標)」と、それを達成するための中間指標である「KPI(重要業績評価指標)」にまで落とし込みます。これにより、施策の優先順位が明確になり、開催後の効果測定も的確に行えます。
- (例)BtoBカンファレンスの場合
- KGI: 新規商談化数 30件
- KPI:
- 参加申込数 300名
- 当日参加率 80%(240名)
- アンケート回答付きリード獲得数 200件
- 特定セッションの満足度 90%以上
誰に、何を届けるか?ターゲットと提供価値の具体化
目的が定まったら、次に「誰に(ターゲット)」、「どんな価値を届けるか(コンセプト)」を具体化します。ターゲットの解像度が高ければ高いほど、心に響くコンテンツや効果的な集客アプローチが見えてきます。
- ターゲット設定の例:
- (悪い例)DXに関心のある企業の担当者
- (良い例)従業員500名以上、製造業のマーケティング部門責任者。MAツール導入を検討しているが、具体的な活用イメージが湧かず、他社事例を求めている。
- 提供価値(コンセプト)の例:
- 「明日から使える、製造業のためのMA活用最前線」
- 「失敗事例から学ぶ、DX推進プロジェクトのリアル」
企画の骨子を固める「6W2H」フレームワーク活用術
KGI/KPI、ターゲット、コンセプトが固まったら、「6W2H」のフレームワークで企画の全体像を可視化します。これにより、関係者間での認識齟齬を防ぎ、検討事項の抜け漏れをなくします。
- Why(なぜ): イベントの目的(KGI/KPI)
- With whom(誰と): 主催、共催、協賛、登壇者、協力会社
- Who(誰に): ターゲット参加者
- What(何を): イベントのコンセプト、コンテンツ、プログラム
- When(いつ): 開催日時
- プロのTIPS: BtoB向けなら、業務時間中の火曜~木曜が一般的。競合の大型イベントと重ならないかも必ずチェックしましょう。
- Where(どこで): 開催場所(オンライン/オフライン/ハイブリッド)
- プロのTIPS: オフラインの場合、ターゲットがアクセスしやすいターミナル駅周辺が鉄則です。
- How(どのように): 運営方法、集客手法、配信プラットフォームなど
- How much(いくらで): 予算、参加費
【STEP2:準備編】抜け漏れゼロへ!半年前から始める逆算タスク管理
%20(1).jpg)
企画が固まったら、いよいよ準備フェーズです。成功するイベントは、緻密な準備とスケジュール管理にかかっています。
全体像を把握する!WBSを使ったタスクの洗い出し
カンファレンス運営には、膨大なタスクが存在します。これらを場当たり的に進めるのではなく、「WBS(Work Breakdown Structure)」を用いて全てのタスクを洗い出し、担当者と期限を設定しましょう。
プロのTIPS: 大規模なカンファレンスの場合、準備期間は最低でも半年前から確保します。以下はBtoBカンファレンスのタスク洗い出し例です。
- 会場関連(6ヶ月前~): 会場リサーチ・仮押さえ、レイアウト設計、インフラ(Wi-Fi、電源)確認、本契約
- 登壇者関連(5ヶ月前~): 登壇者リストアップ・打診、出演契約、講演資料の回収・チェック、事前打ち合わせ
- 集客・広報関連(3ヶ月前~): イベントページ制作、プレスリリース配信、SNSアカウント開設・運用、Web広告出稿、共催企業との連携
- 制作物関連(2ヶ月前~): デザインコンセプト決定、各種クリエイティブ(ロゴ、バナー、動画)制作、配布資料・ノベルティ制作
- 運営関連(1ヶ月前~): 運営マニュアル作成、スタッフ手配・教育、機材・備品リスト作成、リハーサル計画
- システム関連(1ヶ月前~): 申込管理システム設定、配信プラットフォーム契約・設定
必携!イベント運営マニュアル作成の3つの極意
運営マニュアルは、単なる手順書ではありません。スタッフ全員が「同じ目標」に向かって「最高のパフォーマンス」を発揮するための”共通言語”です。
- 「5W1H」で指示を具体化する 誰が見ても一読で理解できるよう、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を明確に記述します。曖昧な表現(例:「適宜対応」)は避け、「〇〇の事態が発生した場合、スタッフAは内線XXで責任者Bに連絡する」のように具体的に書きます。
- ポジティブ&ネガティブ シナリオを盛り込む タイムスケジュール通りの完璧な進行(ポジティブシナリオ)だけでなく、起こりうるトラブルとその対処法(ネガティブシナリオ)を必ず記載します。「機材トラブル」「登壇者の遅刻」「急病人発生」など、リアルな事態を想定することが、当日の冷静な対応に繋がります。
- 「理念・行動指針」を共有する マニュアルの冒頭で、イベントの目的や「参加者にどうなってほしいか」という想いを共有しましょう。「私たちは今日、参加者の明日を変えるきっかけを提供します。そのために、常におもてなしの心で接しましょう」といった一文があるだけで、スタッフの当事者意識は大きく変わります。
集客を最大化するプロモーション戦略
どんなに素晴らしいコンテンツを用意しても、ターゲットに届かなければ意味がありません。イベントページの公開をスタートとし、複数のチャネルを組み合わせて継続的に情報を発信しましょう。
- 集客チャネルの例:
- 自社メルマガ、オウンドメディアでの告知
- プレスリリース配信
- SNS(X, Facebook, LinkedInなど)でのハッシュタグ活用
- Web広告(ターゲットを絞ったリスティング広告やSNS広告)
- 共催・協賛企業からの告知協力
- 登壇者自身のSNSでの発信依頼
【STEP3:当日運営編】想定外を乗り越える!スムーズな進行を実現する現場力
%20(1).jpg)
入念な準備を経て、いよいよ本番当日。ここでは、参加者の満足度を最大化し、トラブルを最小限に抑えるための現場での動き方を解説します。
本番前の最終チェック!リハーサルと機材確認のポイント
当日は、開場時間の最低3時間前には主要スタッフが集合し、最終確認を行います。
- リハーサル: 司会進行や登壇者の動き、音響・照明のタイミングなどを、本番さながらに通しで行います。特にセッション間の転換は、時間が押しやすいため重点的に確認しましょう。
- 機材確認: プロジェクター、スクリーン、PC、マイク、スイッチャーなど、全ての機材の動作チェックを入念に行います。予備のPCやケーブル類も必ず準備しておきましょう。
"おもてなし"の第一歩!スマートな受付・誘導オペレーション
受付は、参加者が最初にイベントに触れる重要な場所です。スムーズで丁寧な対応が、イベント全体の印象を左右します。
- スタッフ配置の目安: 参加者100名に対し、受付スタッフ3名(2名で受付、1名は遊撃として列整理や質問対応)が基本です。
- 事前準備: QRコードによる受付システムを導入すると、行列を大幅に緩和できます。また、Wi-Fiのパスワードやお手洗いの場所など、よくある質問への回答(FAQ)を掲示しておくと親切です。
プロが実践するトラブルシューティング術
どんなに準備をしても、当日のトラブルは起こり得ます。重要なのは、慌てず、迅速に対応することです。
- よくあるトラブルと対処法例:
- 「プロジェクターが映らない」: まずはケーブルの再接続を確認。PCの出力設定ミスも多いです。解決しない場合に備え、予備PCと発表資料データは必ず準備しておきましょう。
- 「登壇者が遅刻」: すぐに電話で状況を確認。到着までの時間に応じて、司会者によるトークや、次のセッションの前倒し、休憩時間のアナウンスなどで柔軟に場を繋ぎます。
- 「マイクにノイズが入る」: 電池切れや他電波との干渉が原因のことが多いです。予備の電池や有線マイクを常に準備しておきましょう。
【STEP4:開催後編】次につなげる!イベント価値を最大化するフォローアップ
%20(1)%20(1).jpg)
イベントは終了時がゴールではありません。開催後のフォローアップこそ、イベントの価値を最大化し、次の成功に繋げるための重要なプロセスです。
カンファレンス以外のイベント形式について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。コンベンション、レセプションそれぞれの特徴や成功のポイントを解説しています。
効果測定とデータ分析で成果を可視化する
まず、企画時に設定したKGI/KPIがどの程度達成できたのかを、具体的な数値で振り返ります。
- 分析するデータの例:
- 最終参加者数、参加率
- アンケート回答数、回答率
- 各セッションの視聴数、満足度
- SNSでのハッシュタグ投稿数、エンゲージメント
- ウェブサイトへのアクセス数
- 獲得リード数、商談化数
これらのデータを分析し、「なぜこのセッションは人気だったのか」「どの集客チャネルが最も効果的だったのか」といった成功・失敗要因を明らかにします。
熱量を保つ!参加者へのお礼メールとアンケート術
参加者の熱量が高いうちに、24時間以内を目安にお礼メールを送りましょう。感謝の気持ちと共に、アンケートへの協力を依頼します。
すぐに使える!お礼メール例文 件名:【株式会社REIGETSU】「〇〇カンファレンス」ご参加の御礼
〇〇〇様
この度は、〇月〇日に開催いたしました「〇〇カンファレンス」にご参加いただき、誠にありがとうございました。
当日は、〇〇様をはじめ多くの皆様にご参加いただき、盛況のうちに会を執り行うことができましたこと、心より御礼申し上げます。
よろしければ、今後のより良いイベント運営の参考とさせていただきたく、 1分ほどで完了する簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。 ▼アンケートはこちら [アンケートURL]
また、当日の講演資料は以下よりダウンロードいただけます。 ぜひ、貴社のビジネスにお役立てください。 ▼講演資料のダウンロードはこちら [資料ダウンロードURL]
末筆ではございますが、〇〇様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
株式会社REIGETSU [署名]
プロのTIPS: アンケートでは、「イベントで最も学びになった点」や「今後聞いてみたいテーマ」など、次回の企画に繋がる具体的な質問を入れることが重要です。
社内への成果報告とナレッジの蓄積
データ分析の結果と参加者からのフィードバックをまとめ、関係者への成果報告会を実施します。成功体験だけでなく、課題や反省点もオープンに共有することで、組織全体のノウハウとして蓄積されます。今回作成した運営マニュアルに、当日の気づきや改善点を追記し、「生きたマニュアル」としてアップデートしていくことを忘れないでください。
カンファレンス運営に課題を感じたら、プロに相談という選択肢も
ここまで、カンファレンス運営を成功させるための具体的なロードマップをご紹介しました。しかし、
- 「コア業務が忙しく、イベント準備に十分なリソースを割けない」
- 「より戦略的で、事業成果に直結するカンファレンスを実現したい」
- 「オンラインやハイブリッドなど、新しい形式の運営ノウハウがない」
といった課題をお持ちの担当者様も多いのではないでしょうか。
そのような時は、イベント制作の専門家集団である株式会社REIGETSUにぜひご相談ください。
私たちは、単にイベントを運営するだけではありません。お客様のビジネスゴール達成を第一に考え、企画立案から緻密なプロジェクト管理、当日のディレクション、開催後の効果測定までをワンストップで伴走支援いたします。
数々の大手企業のカンファレンスを手掛けてきた実績とノウハウを活かし、貴社のイベントを「忘れられない成功体験」へと導くことをお約束します。
まずは、貴社が抱える課題やご要望を、お気軽にお聞かせください。 初回のご相談は無料です。
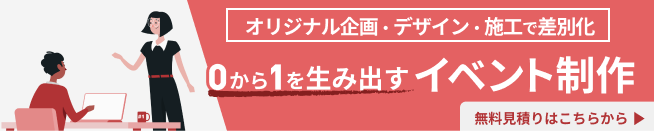
ライター 松井あや
航空会社にて約20年間勤務。接客・マニュアル作成・人材育成に携わった後、現在はフリーランスとして展示会・イベントの司会業を行いながら、在宅でライターとして活動中。