「共催」とは?イベント開催形態の違いと役割分担について調べてみました

イベントを開催する際、主催、共催、協賛、協力、後援など、様々な開催形態があります。それぞれの形態には特徴があり、イベントの目的に合わせて適切な形態を選択することが重要です。特に、共催イベントの場合は、複数の団体が協力して企画・運営を行うため、パートナーとの信頼関係構築と役割分担の明確化が鍵となります。 本記事では、イベント開催の基本となる共催の概要を解説した上で、主催、協賛、協力、後援など、他の開催形態との違いを明らかにします。さらに、イベントの目的に合わせた開催形態の選択方法や、企画・運営を専門家に任せるメリットについて詳しく説明します。イベント開催を検討されている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
監修 管理本部 部長 石橋和将
イベントの企画から運営まで一貫して指揮を執り、幅広いジャンル・規模の案件に対応してきました。これまでに、国際フォーラムや業界展示会、企業向けセミナー、地域振興イベントなど、多様なイベントの統括・運営を担当。大規模なカンファレンスや就職イベント、スポーツ関連プロジェクトなどの進行管理にも豊富な経験を持ちます。
目次
-
共催とは?イベント開催形態の基本を理解しよう
-
・共催とは?その定義と役割
-
・共催イベントの事例
-
・共催のメリットとデメリット
-
-
主催、協賛、協力、後援の意味と役割の違いを解説
-
・主催の定義と役割
-
・協賛、協力、後援の定義と違い
-
-
イベントの目的に合わせた参加形態の選択方法
-
・イベントの目的と参加形態の関係性
-
・各参加形態の特徴と適した状況
-
・参加形態選択のポイントと留意点
-
-
イベントの企画・運営はREIGETSUに丸投げがおすすめ
共催とは?イベント開催形態の基本を理解しよう

共催とは?その定義と役割
共催とは、複数の団体や企業が対等な立場でイベントを企画・運営する形態を指します。各団体が持つ資源やノウハウを持ち寄ることで、イベントの目的達成に向けて協力します。
共催を行う企業の役割として、以下のような点が挙げられます。
- 会場の手配
- 広報活動
- 講演者の選定
- 予算管理
これらの役割を分担し、互いの強みを活かしてイベントを成功に導くのが共催の特徴です。例えば、IT企業と教育機関が技術セミナーを共催する場合、IT企業は最新技術の知見を提供し、教育機関は会場や参加者の集客力を担うことができます。
共催イベントの事例
共催は多様な分野で実施されており、それぞれの強みを活かしたイベントが多数開催されています。ここでは、具体的な共催イベントの事例をご紹介します。
1.物流人事サミット
- 主催: 株式会社ギオン、株式会社PR TIMES、株式会社令和PR
- 共催: アサヒロジスティクス株式会社、花王ロジスティクス株式会社
- 概要: 物流業界の認知を変えることを目指し、3社の取り組み紹介、広報活動による採用課題解決事例の共有、パネルディスカッションを実施。業界のイメージ向上と採用促進に貢献しました。
- イベントページ: https://note.com/quiet_tern6604/n/n0001d72ffd2c
2.ハタチの選択
- 共催企業名: 明治大学、Original Point
- 概要: 就職活動を控える若者に対し、多様なキャリアを歩む社会人をゲストに招き「大手VSベンチャー」「企業VS転職VS副業」「元人事対談」といった切り口で、一般的な就活イベントでは語られない将来の選択肢を広げる機会を提供しました。
- イベントページ: https://originalpoint.co.jp/report/5271
3.第21回さがみはら環境まつり
- 主催: さがみはら環境まつり実行委員会
- 共催: 相模原市
- 概要: 環境保全活動の紹介ブース展示や体験型企画を通じて、来場者が楽しみながら環境問題について学べるイベントです。行政と市民団体が連携し、地域全体の環境意識向上に貢献しています。
- イベントページ: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000456.000072959.html
4.京都広報会議ミートアップイベント「公務員はオワコンなのか?―ローカルから届ける公務員のリアル―」
- 共催企業名: 京丹波町(Kyotamba Innovation Lab)、福知山市
- 概要: 「自治体広報のあり方」をテーマに、公務の枠を超えて地域で挑戦を続けるパラレルキャリア型職員や、Z世代公務員が登壇し、講演やトークセッションを実施。地域における公務員の新たな役割を発信しました。
- イベントページ: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000053572.html
5.さのアキカツサポーター 古民家活用実践編
- 主催: 株式会社情報都市
- 共催: 一般社団法人 全国古民家再生協会 大阪第二支部
- 概要: 築100年以上の古民家を舞台に、実践的な古民家の活用方法を学ぶ体験型イベントです。地域活性化と古民家保存の啓発に繋がっています。
- イベントページ: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000089492.html
6.Cinema at Sea関連企画 VR体験上映
- 主催: NPO法人Cinema at Sea
- 共催: 株式会社リトルユニバース
- 概要: Cinema at Sea - 沖縄環太平洋国際映画祭の関連イベントとして、「VR映画」という新しい映画鑑賞スタイルを提供。従来のスクリーンでは味わえない没入感のある体験を通じて、映像コンテンツの可能性を広げました。
- イベントページ: リトルユニバースオキナワ / Cinema at Sea
7.HOMECOMING PARK 城南島海浜公園
- 共催: 城南島海浜公園 / ペットゴー株式会社 / 一般社団法人 Do One Good
- 概要: 動物保護団体から巣立った卒業犬たちの里帰りイベントです。新たな家族を待つ保護犬たちのことを広く知ってもらい、参加者が楽しめる様々な企画も実施しています。動物愛護の啓発と、保護犬の家族探しを支援しています。
- イベントページ: https://doonegood.jp/hcp/
8.海洋都市横浜 うみ博2025
- 主催: 海洋都市横浜うみ協議会
- 共催: 横浜市
- 概要: 開催10年目を迎え「横浜から未来のうみをつくろう」をコンセプトに、海に関わる研究機関、企業、大学、行政が一体となり、展示ブース、ワークショップ、船の見学など様々な体験を通して、横浜ならではの海の魅力を発信しています。
- イベントページ: https://umihaku.jp
9.PROTON EXPO 2025
- 主催: プロトングループ(株式会社菱豊フリーズシステムズ/株式会社新鮮ネットワーク)
- 共催: プロトングループ取引先企業 約50社
- 概要: 「未来の食卓を冷凍で彩る『美味しいネットワーク』」をテーマに、革新的な技術と商材をサポートするプロトングループの活動を紹介。全国の産地連携によって生まれた高品質な冷凍食品の展示・試食・体験を提供しています。
- イベントページ: https://www.proton-01.com/expo2025/
10.WaytoAGI Global AI Conference 2025ー東京
- 主催: WaytoAGI
- 共催: 桜美林大学
- 概要: 世界中からAIのパイオニアが集結し、技術と創造性の未来を探求。産業界、政府、学術界など様々な分野のリーダー間の知識交流を深めることを目的に、講演、展示、AI初心者向けワークショップなどを実施します。
- イベントページ: https://tokyo.waytoagi.com/
共催のメリットとデメリット
共催にはいくつかのメリットがあります。まず、単独で開催するよりも費用や労力を分散できます。また、互いのネットワークを活用することで集客力を高めることができます。さらに、異業種との共催では新たなアイデアやビジネスチャンスが生まれる可能性もあるでしょう。
一方、デメリットも存在します。意思決定や責任分担が複雑になりがちなことや、利害関係が対立した場合の調整が難しいことが挙げられます。これらのデメリットを軽減するためには、事前に役割分担や意思決定プロセスを明確にしておくことが重要です。
以上、共催の基本的な概念と特徴について理解を深めました。次章では、他のイベント開催形態との違いを詳しく見ていきましょう。
主催、協賛、協力、後援の意味と役割の違いを解説
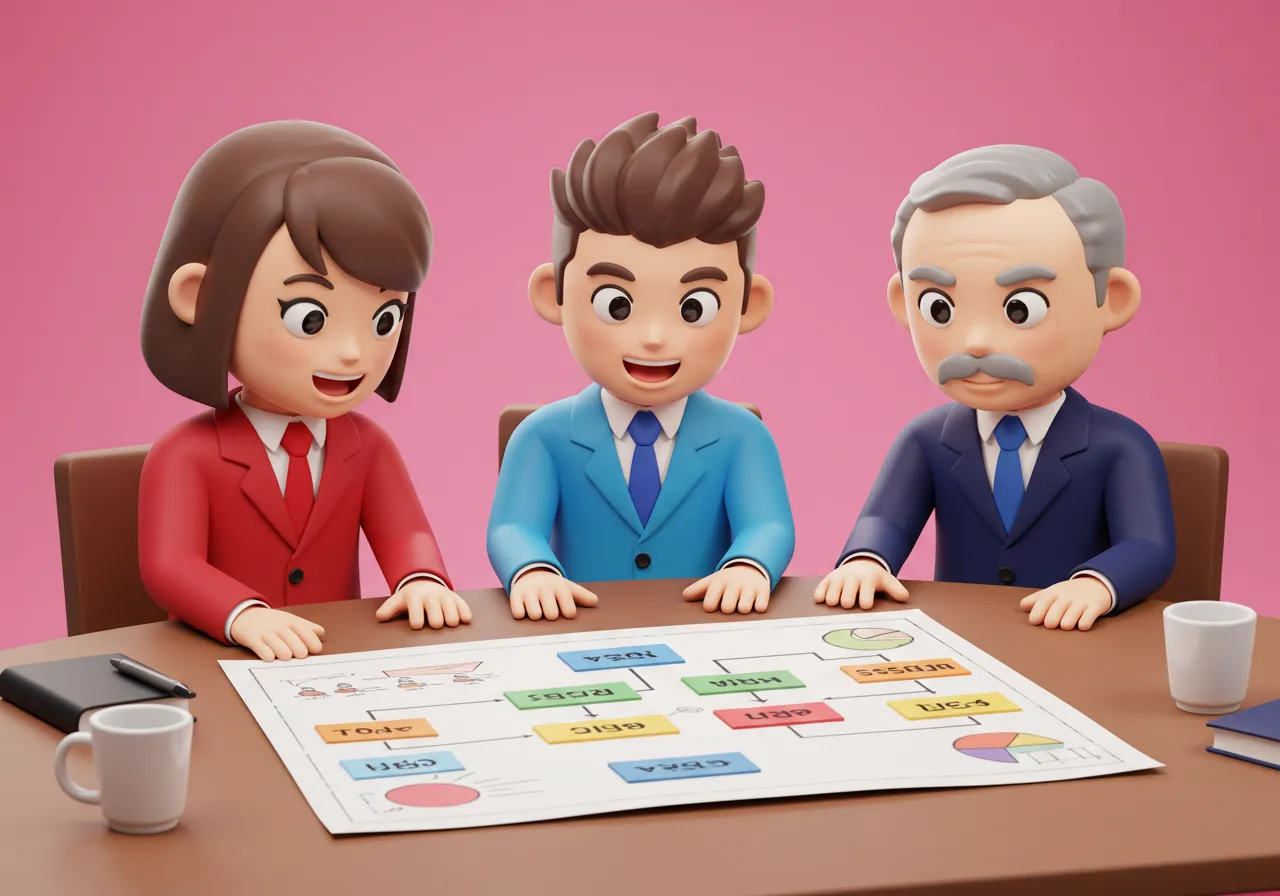
前章で共催について理解を深めましたが、イベント開催には他にも様々な形態があります。ここでは、主催、協賛、協力、後援の意味と役割の違いについて解説します。
共催のなかでも、特定のテーマに絞って専門的な知識や情報を共有し、参加者同士の交流を深めるカンファレンスを開催することもあります。カンファレンスについてより詳しく知りたい方は、カンファレンスとは?その意味から企画~開催の流れまで徹底解説もあわせてご覧ください。
主催の定義と役割
主催とは、イベントの企画・運営において中心的な役割を担う団体や企業のことを指します。主催者は、イベントの目的設定、予算管理、広報活動、当日の運営など、全体的な責任を負います。
主催者の役割は以下の通りです。
- イベントの目的や内容の決定
- 予算の確保と管理
- 会場の手配
- 参加者の募集と管理
- 当日の運営とトラブル対応
主催者は、イベントの成否に大きく関わる重要な立場であると言えます。
主催者としてイベントを成功させる手順とポイントは、ピッチイベントとは?主催者目線で成功に導く手順とポイントを徹底解説で詳しくご紹介しています。
協賛、協力、後援の定義と違い
協賛、協力、後援は、イベントを支援する立場ですが、それぞれ意味合いが異なります。
協賛は、イベントに必要な資金や物資を提供する代わりに、広告宣伝の機会を得る形態です。協賛企業は、イベントの規模や内容に応じて協賛金を支払い、会場での看板掲示やチラシへの社名掲載などの特典を得ます。
一方、協力はイベントの運営を人的・物的に支援する形態です。協力団体は、スタッフの派遣、機材の貸与、会場の提供などを通じてイベントをサポートします。ただし、協力団体は主催者ほどの責任は負いません。
そして後援は、イベントの趣旨に賛同し、名義を連ねる形態です。後援団体は、イベントの信頼性を高める役割を果たしますが、資金的な支援は行いません。
以上のように、主催、協賛、協力、後援は、それぞれイベントに対する関わり方が異なります。イベントの目的や規模に応じて、適切な形態を選択することが重要です。次章では、イベントの目的と開催形態の関係性について詳しく解説していきます。
イベントの目的に合わせた参加形態の選択方法
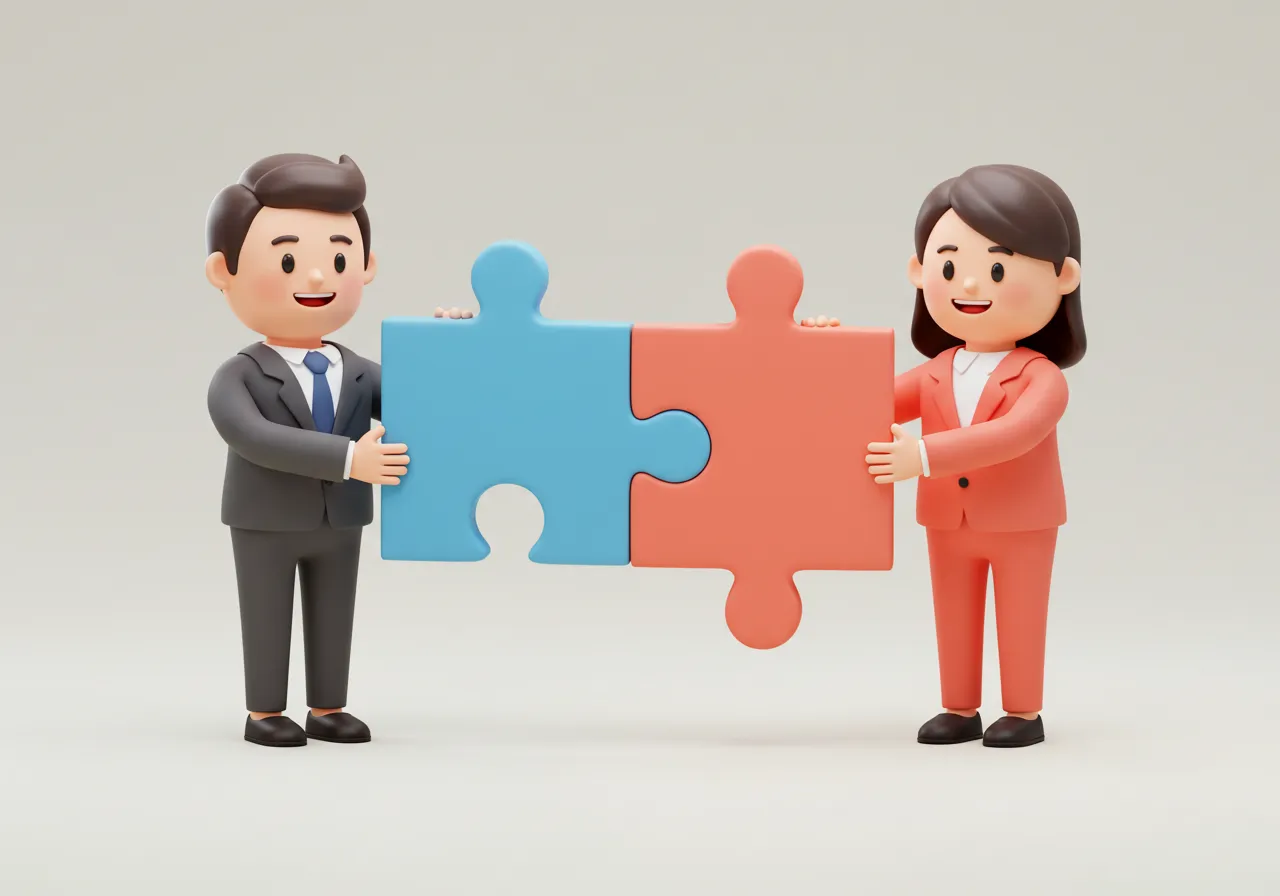
イベントを成功させるためには、目的に合わせて適切な参加形態を選択することが重要です。ここでは、共催を含めた各開催形態とイベントの目的の関係性、各形態の特徴と適した状況、選択のポイントと留意点について見ていきます。
イベントの目的と参加形態の関係性
イベントの目的は多岐にわたりますが、それぞれに適した開催形態があります。例えば、新製品発表会には主催または共催が適しています。ブランドイメージ向上イベントでは主催または協賛が効果的です。ネットワーキングイベントでは共催や協力が選ばれることが多く、セミナーや講演会では主催、共催、後援が適しています。
各参加形態の特徴と適した状況
主催は、イベントの全体的な責任を負う形態であり、目的達成に向けて主体的に動ける点が強みですが、全ての面で負担が大きくなります。
共催は、複数の団体が協力してイベントを運営する形態です。資源の分散や、互いのネットワークを活用した集客が可能となる一方、意思決定や調整に時間がかかる場合があります。共催は、単独開催が難しい場合や、異業種との連携によるシナジー効果を狙う場合に適しています。
協賛は、資金提供の代わりに広告宣伝の機会を得る形態であり、イベントの規模拡大に役立ちます。協力は、人的・物的なサポートを得られる形態で、運営負担の軽減につながります。後援は、イベントの信頼性を高める形態であり、参加者の安心感につながります。
大規模な集会であるコンベンションは、業界の活性化やネットワーク構築に大きなメリットをもたらします。開催で得られるメリットや企画の進め方は、企業必見!コンベンション開催で得られる3つのメリットと企画の進め方で詳しく解説しています。
参加形態選択のポイントと留意点
目的に合わせて参加形態を選択する際は、目的達成に必要な資源の確保、各形態のメリット・デメリットの理解、パートナー選びの重要性を押さえましょう。特に共催の場合は、パートナーとの信頼関係構築と、役割分担の明確化が重要です。
参加形態選択後も、綿密な計画と関係者との円滑なコミュニケーションを通じて、イベントの目的を共有し、合意形成を図ることが求められます。
イベントの成功には、目的に合わせた適切な参加形態の選択が重要です。次章では、イベントの企画・運営を円滑に進めるための提案を紹介します。
イベントの企画・運営はREIGETSUに丸投げがおすすめ
イベントの目的に合わせて適切な参加形態を選択することの重要性について理解を深めてきましたが、実際の企画・運営となると、専門的な知識と経験が必要不可欠です。そこで、イベントの企画・運営は専門家に任せることをおすすめします。
REIGETSUは、イベント企画・運営のプロフェッショナル集団です。豊富な実績と知見を活かして、クライアントの目的に合わせたイベントを提案し、実現します。主催、共催、協賛、協力、後援など、あらゆる形態のサポートが可能です。
イベントの開催形態には主催、共催、協賛、協力、後援などがあり、それぞれ特徴が異なります。イベントの目的に合わせて適切な形態を選択することが重要ですが、実際の企画・運営は専門家に任せることで、効果的かつ効率的なイベント実現が可能となります。特に、共催イベントの場合、REIGETSUがパートナー間の調整役を務めることで、スムーズな企画・運営が可能となります。
イベントの成功には、専門家の力を借りることが欠かせません。目的達成に向けて、ぜひREIGETSUにイベントの企画・運営を丸投げすることをおすすめします。

ライター 藤花しおん
金融、美容、旅行、グルメなど多分野で執筆。2016年からはエンタメ系オウンドメディアに編集者として活動。